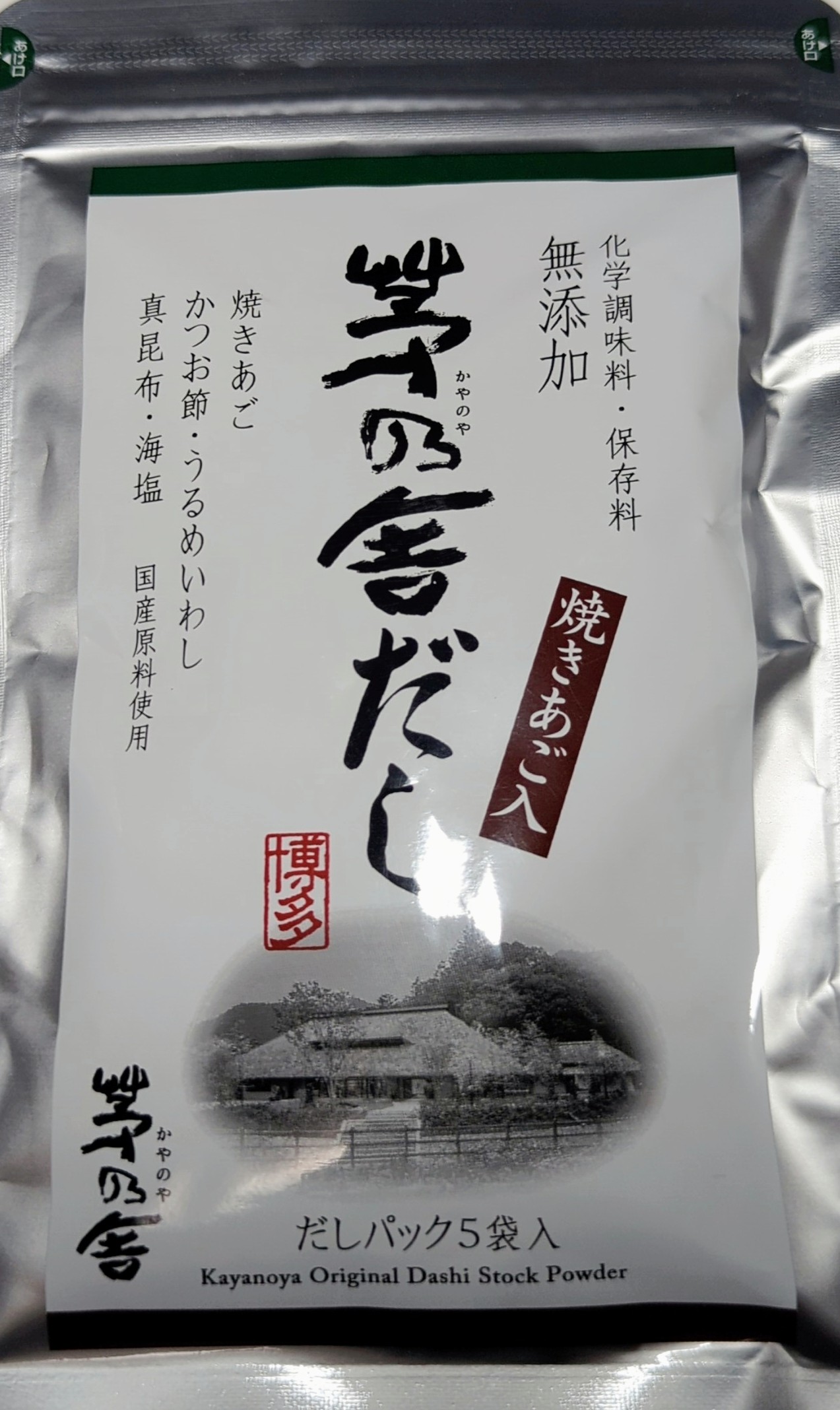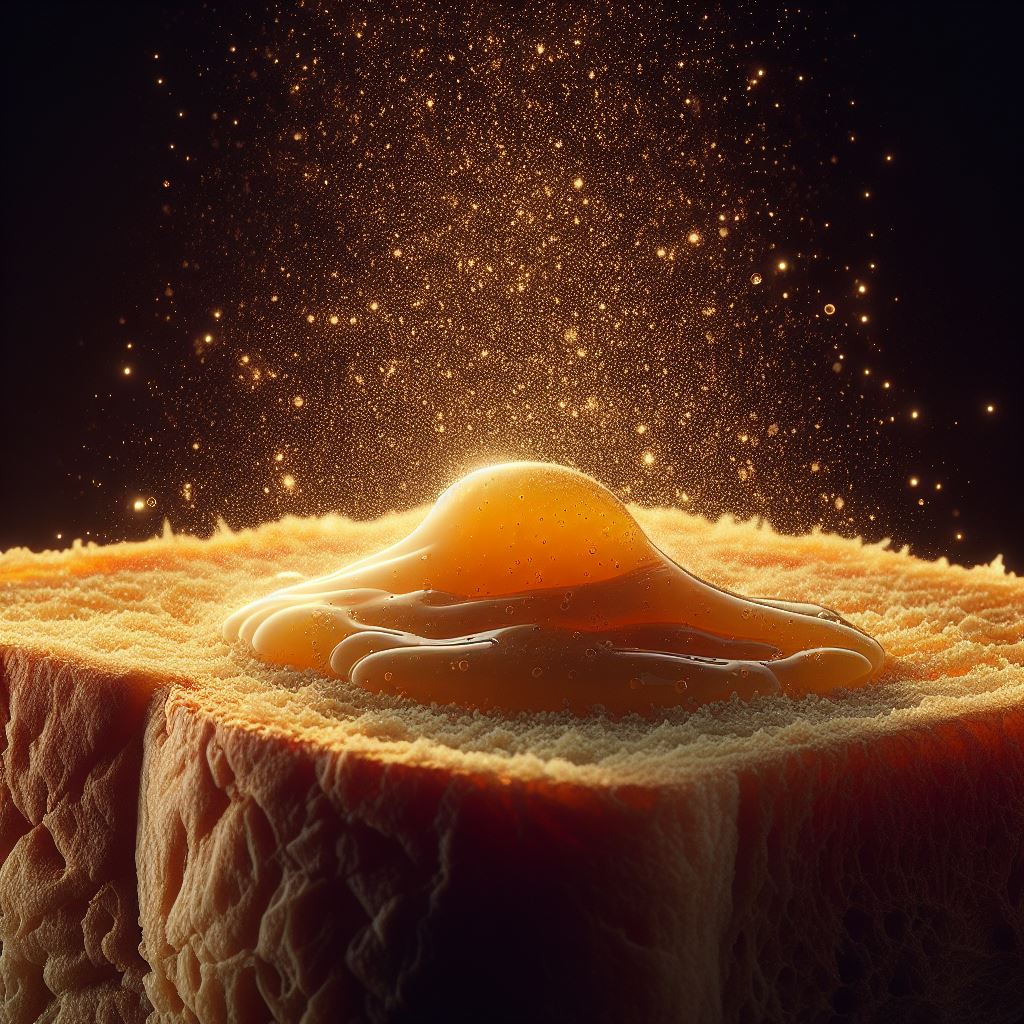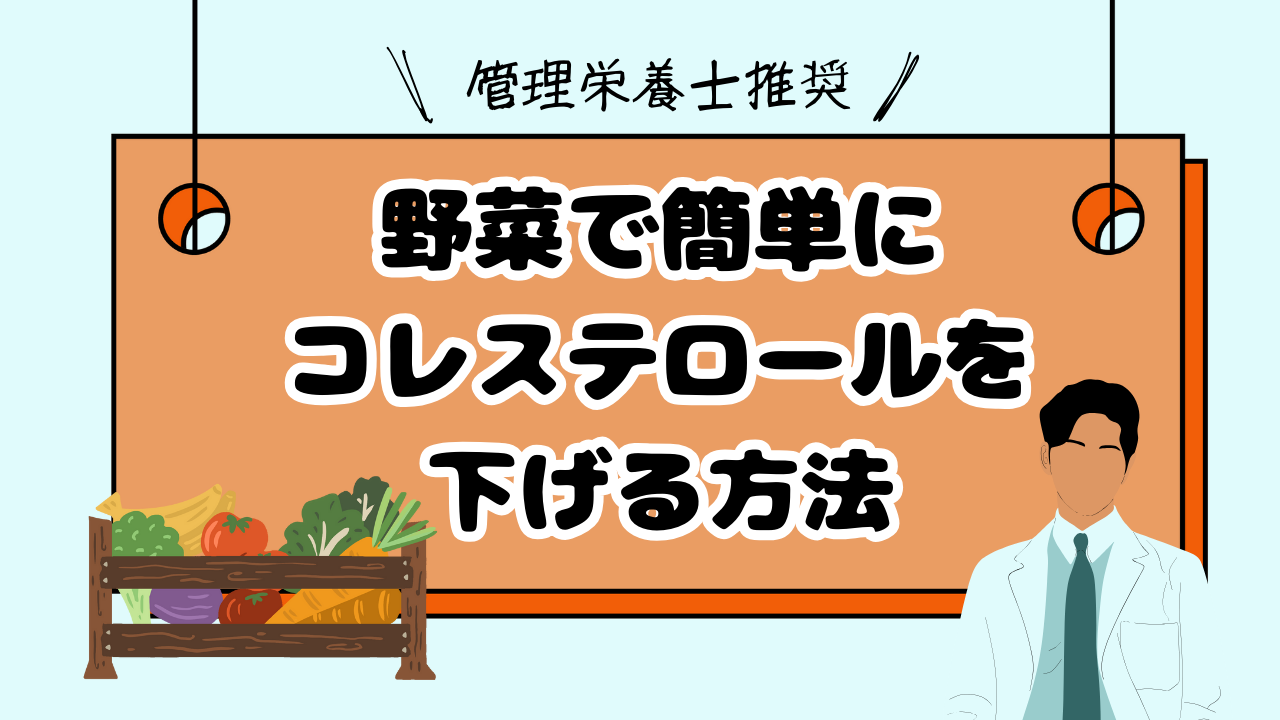
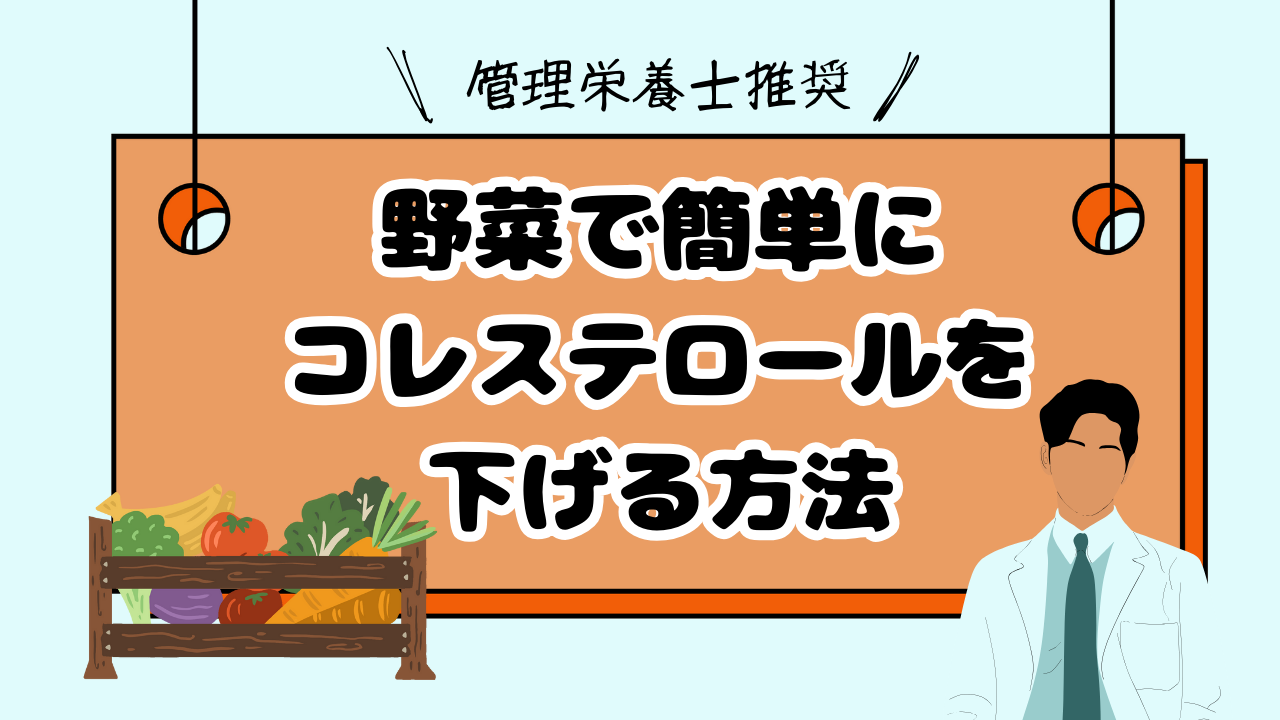
【管理栄養士推奨】野菜で簡単にコレステロールを下げる方法
【管理栄養士推奨】トクホのコレステロールを下げる飲み物
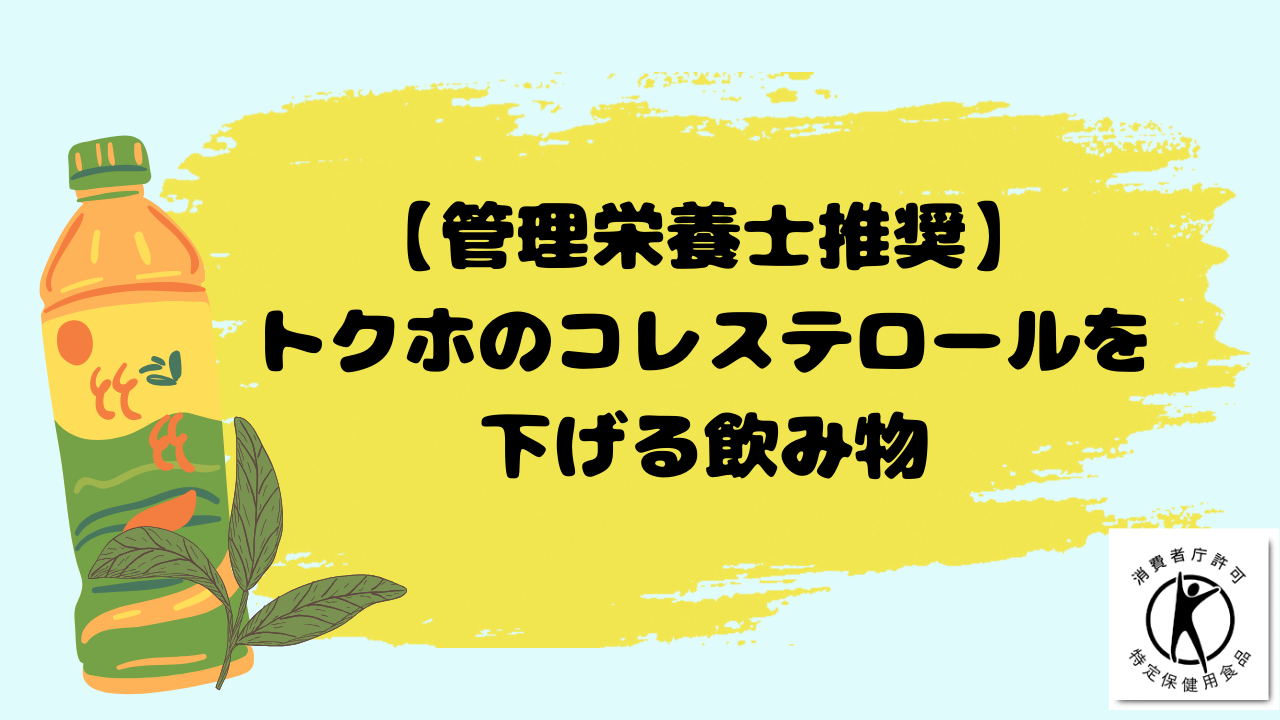
コレステロールは、体に必要な脂質の一種ですが、過剰になると動脈硬化や心血管疾患のリスクを高めます。コレステロールを下げるためには、食事や運動などの生活習慣の改善が重要ですが、仕事や育児で多忙な中、現実的に体に必要な栄養全てを取り入れることが難しい方もいらっしゃると思います。そんな場合は、コレステロールを下げる野菜や果物が凝縮された飲み物も有効な手段の一つです。野菜の力でコレステロールを下げる「緑でサラナ」は、管理栄養士が推奨する商品です。
今回は、コレステロールが気になる方におすすめの特定保健用食品「緑のサラナ」について、原材料やその効果、効果を高める飲み方などを管理栄養士が詳しくご紹介します。
緑でサラナとは?

緑でサラナとは、サンスターが販売しているコレステロールを下げる野菜の力(SMCS)が含まれた特定保健用食品(トクホ)です。この飲料には、ブロッコリーやキャベツなどのアブラナ科野菜に多く含まれる成分であるSMCS(天然アミノ酸:S-メチルシステインスルホキシド)が1缶あたり26mg含まれています。SMCSには、コレステロールを胆汁酸に変える酵素を活性化することにより、血中コレステロールを下げる働きがあります。
コレステロールは、細胞膜の構成成分やホルモンの原料として必要な物質ですが、過剰になると動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などのリスクを高めます。 コレステロールには、LDL(悪玉)コレステロールとHDL(善玉)コレステロールの2種類がありますが、特にLDLコレステロールが高いと血管に沈着しやすくなります。 一般的に、LDLコレステロールは120mg/dL以下、HDLコレステロールは40mg/dL以上が望ましいとされています。
緑でサラナは、ヒト試験で1日2缶飲み続けることで3週間目以降からLDLコレステロールを低下させる結果が出ており、コレステロールが気になる方や高めの方に適しています。
緑でサラナは青汁?野菜ジュース?どっち?
緑でサラナは青汁でも野菜ジュースでもありません。緑でサラナは、コレステロールを下げる効果があるブロッコリー・キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)を含む特定保健用食品です。青汁や野菜ジュースは、一般的には野菜の栄養素を摂取するための飲料ですが、特定保健用食品は、消費者庁の許可を得た機能性表示食品で、科学的根拠に基づいて特定の機能性を表示することができます。緑でサラナは、1日2缶飲み続けることで3週間目以降からLDL(悪玉)コレステロールを低下させる結果がヒト試験で出ています。青汁や野菜ジュースには、このような効果はありません。ですから、緑でサラナは青汁や野菜ジュースとは異なる飲料と言えます。
緑でサラナのカロリーは?野菜ジュースと比較してみた
コレステロールが気になる方や野菜不足が心配な方におすすめの特定保健用食品「緑でサラナ」。野菜の力(SMCS)でLDL(悪玉)コレステロールを下げる効果があるとされていますが、そのカロリーはどのくらいなのでしょうか?また、一般的な野菜ジュースと比べてどうなのでしょうか?管理栄養士が詳しく解説します。
緑でサラナのカロリーは1缶あたり53kcal
緑でサラナのカロリーは、1缶(160g)あたり53kcalです。砂糖や食塩、香料や保存料は一切不使用で、原材料由来の糖類が含まれています。たんぱく質は1g、脂質は0g、炭水化物は12.8g、食物繊維は1.2gです。また、カリウムやビタミンKなどの野菜由来の栄養素も含まれています。
野菜ジュースのカロリーは1缶あたり約100kcal
一方、市販の野菜ジュースのカロリーは、1缶(190g)あたり約100kcalです。砂糖や食塩、香料や保存料などの添加物が含まれている場合が多く、原材料由来の糖類以外にも糖類が加えられている場合があります。たんぱく質は1.4g、脂質は0.1g、炭水化物は23.8g、食物繊維は1.9gです。カリウムやビタミンKなどの栄養素も含まれていますが、緑でサラナよりも少ない場合が多いです。
緑でサラナは野菜ジュースよりも低カロリーで栄養価が高い
以上の比較から、緑でサラナは野菜ジュースよりも約半分のカロリーで、栄養価が高いことがわかります。野菜ジュースは飲みやすいように甘みや塩味が加えられていることが多く、カロリーが高くなりがちです。また、野菜ジュースは野菜の種類や量によって栄養素の含有量が異なりますが、緑でサラナは8種類の青野菜と2種類の果物をバランスよくブレンドしており、コレステロール低下作用のあるSMCSを含んでいます。コレステロールが気になる方や野菜不足が心配な方は、緑でサラナを飲むことで、低カロリーで野菜の力を摂取できるというメリットがあります。
まとめ:緑でサラナは野菜ジュースの代わりにおすすめ
緑でサラナのカロリーは1缶あたり53kcalで、野菜ジュースの約半分です。また、緑でサラナは野菜ジュースよりも栄養価が高く、コレステロール低下作用のあるSMCSを含んでいます。野菜ジュースは飲みやすいですが、カロリーが高くなりがちで、栄養素の含有量も不安定です。コレステロールが気になる方や野菜不足が心配な方は、緑でサラナを野菜ジュースの代わりに飲むことで、低カロリーで野菜の力を摂取できるということがわかりました。緑でサラナは特定保健用食品なので、1日2缶を目安に飲むことが推奨されています。野菜の力でコレステロールを下げる緑でサラナをぜひお試しください。
緑でサラナの原材料は?8種類の青野菜と2種類の果物をブレンド
緑でサラナの原材料は、8種類の青野菜と2種類の果物をブレンドしたものです。具体的には、以下のような野菜と果物が使われています。
- 野菜(ブロッコリー、セロリ、キャベツ、レタス、ほうれん草、大根葉、小松菜、パセリ)
- 果物(りんご、レモン)
これらの野菜と果物には、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれており、健康や美容にもよい影響が期待できます。 例えば、ブロッコリーやキャベツには、抗酸化作用や免疫力向上、がん予防などに関与するとされるスルフォラファンという成分があります。 セロリやレタスには、利尿作用や血圧降下作用があるとされるカリウムが多く含まれています。 ほうれん草や小松菜には、血液の酸素運搬能力を高める鉄や、骨や歯の形成に必要なカルシウムが豊富に含まれています。 パセリには、ビタミンCやビタミンK、葉酸などのビタミン類が多く含まれており、肌や粘膜の健康維持や血液の凝固防止、赤血球の生成などに役立ちます。りんごには、食物繊維の一種であるペクチンが多く含まれており、便秘の改善やコレステロールの排出、血糖値の上昇抑制などに効果があるとされています。 レモンには、ビタミンCやクエン酸が多く含まれており、疲労回復や代謝促進、美肌効果などに効果があるとされています。
緑でサラナは、1缶に約100g相当の野菜が入っており、2缶飲用するとバナナ約3本分の食物繊維が摂取できます。 野菜不足が気になる方にもおすすめです。
緑でサラナは無添加?副作用やアレルギーの危険性は?
緑でサラナは、保存料や香料、食塩、砂糖は一切不使用の無添加食品です。 これらの添加物は、食品の味や色、香り、賞味期限などを改善するために使われることがありますが、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。 例えば、保存料は食品の腐敗や変色を防ぐために使われますが、アレルギーの原因になったり、善玉菌の働きを阻害したりすることがあります。 香料は食品の香りを強化するために使われますが、化学合成されたものは舌が麻痺して味覚が鈍くなったり、頭痛や吐き気などの副作用を引き起こしたりすることがあります。 食塩は食品の味を調えるために使われますが、過剰に摂取すると高血圧やむくみなどの原因になったり、カルシウムの排出を促進して骨粗しょう症のリスクを高めたりすることがあります。 砂糖は食品の甘みを与えるために使われますが、過剰に摂取すると肥満や糖尿病などの生活習慣病の原因になったり、虫歯や肌荒れなどのトラブルを引き起こしたりすることがあります。
緑でサラナは、これらの添加物を一切使用せずに、野菜と果物の自然な味や栄養をそのまま楽しめる飲料です。 ただし、原材料由来のアレルゲン(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)が含まれる可能性があることに注意してください。 また、緑でサラナは、コレステロールを下げる効果があるとしても、それだけで高コレステロール血症や動脈硬化などの病気を予防するものではありません。 健康な生活習慣を心がけることが大切です。
緑でサラナは一日何本?いつ飲むのが効果的?
緑でサラナの飲み方は、1日2本を目安に、食事と一緒に飲むのがおすすめです。 食事と一緒に飲むことで、食事中に摂取したコレステロールの吸収を抑えることができます。 また、食事と一緒に飲むことで、野菜と果物の栄養素の吸収も効率的になります。 例えば、ビタミンCは、鉄の吸収を促進する働きがあります。 ビタミンKは、カルシウムの骨への取り込みを助ける働きがあります。 これらのビタミンは、緑でサラナに含まれる野菜や果物に豊富に含まれていますが、水溶性のために体内に蓄積されにくく、摂取したらすぐに排出されてしまいます。 そのため、食事と一緒に飲むことで、必要なタイミングで必要な量のビタミンを摂取することができます。
緑でサラナは、冷やして飲むとさわやかな味わいが楽しめます。 また、牛乳やヨーグルトなどと混ぜて飲むと、さらに栄養価が高まります。 例えば、牛乳やヨーグルトには、カルシウムやタンパク質などの栄養素が多く含まれており、骨や筋肉の健康に役立ちます。 また、ヨーグルトには、腸内環境を整える乳酸菌が含まれており、便秘や下痢の予防や改善に効果があるとされています。 ただし、牛乳やヨーグルトには、コレステロールや脂肪が含まれているので、摂り過ぎに注意してください。
緑でサラナは効果ない?コレステロールを下げる期間はどれくらい?
コレステロールが気になる方や高めの方におすすめの特定保健用食品「緑でサラナ」ですが、本当に効果はあるのでしょうか?また、実際にコレステロールを下げるにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか? ここでは、緑でサラナのコレステロール低下効果について、科学的な根拠と実際の体験談をもとに解説します。
緑でサラナの効果は科学的に証明されている
緑でサラナの効果は、特定保健用食品(トクホ)として消費者庁に認められています。トクホとは、身体の生理的な働きに影響を与える保健機能成分を含む食品で、有効性や安全性が厳しく審査されたものです。緑でサラナの場合、コレステロール値を下げる効果があるという表示が許可されています。
緑でサラナのコレステロール値を下げる効果は、SMCSというブロッコリー・キャベツ由来の天然アミノ酸によるものです。SMCSは、肝臓で胆汁酸に変化させる酵素を活性化し、体外に排出されるコレステロールの量を増やすことで、コレステロールを下げます。このSMCSの作用は、ヒト試験で確認されており、1日2缶飲用することで、3週間目からLDL(悪玉)コレステロールが低下する結果が出ています。
緑でサラナのコレステロール低下効果のメカニズム
緑でサラナのコレステロール低下効果の秘密は、ブロッコリーとキャベツに由来する天然アミノ酸の一種、SMCS(S-メチルシステインスルホキシド)にあります。 SMCSは、肝臓でコレステロールを胆汁酸に変える酵素を活性化することで、体外に排出されるコレステロールの量を増やす働きがあります。 これにより、血中のLDL(悪玉)コレステロールを低下させることができます。 緑でサラナは、1缶あたり26mgのSMCSを含んでいます。
緑でサラナのコレステロール低下効果の臨床試験の結果
緑でサラナのコレステロール低下効果は、臨床試験で確認されています。 サンスターの研究によると、LDLコレステロールが高めの成人男女(平均値約155mg/dl)に、1日2缶の緑でサラナを12週間飲んでもらったところ、3週間目以降からLDLコレステロールが有意に低下(約145mg/dl)したという結果が得られました。 この試験は、9月から12月にかけて実施されたもので、コレステロールが上昇しやすい季節においても、緑でサラナの効果が示されたということになります。
緑でサラナのコレステロール低下効果の実際の体験談
緑でサラナのコレステロール低下効果は、臨床試験だけでなく、実際に飲んだ方々の体験談でも証明されています。 例えば、以下のような口コミがあります。
「緑でサラナを飲み始めてから、コレステロール値が下がりました。 以前は200を超えていたのが、今は160台になりました。 味も飲みやすくて、毎日続けられます。」
「コレステロールが高くて、医師から薬を処方されましたが、副作用が心配でした。 緑でサラナを試してみたところ、3ヶ月でコレステロールが30ポイントも下がりました。 薬を飲まなくても済むようになりました。」
「緑でサラナを飲んでいると、野菜不足も解消されます。 野菜の味がするので、食事の前に飲むと満足感があります。 コレステロールも下がって、体調も良くなりました。」
緑でサラナでコレステロールを下げるには3週間以上が目安
以上のように、緑でサラナは、ブロッコリーとキャベツ由来の天然アミノ酸SMCSによって、コレステロールを下げる効果があることが科学的にも実践的にも証明されています。 ただし、効果には個人差がありますし、飲み方や食生活などにも影響されますので、一概に言えるものではありません。 しかし、一般的には、緑でサラナを1日2缶飲み続けることで、3週間目以降からコレステロールが低下する傾向にあると言えるでしょう。 もちろん、緑でサラナだけでなく、バランスの良い食事や適度な運動など、コレステロールケアには総合的な対策が必要です。 緑でサラナは、その一助としてお役立てください。
緑でサラナの賞味期限は?その理由と注意点
緑でサラナは、コレステロールを下げる野菜の力(SMCS)を含んだ日本で唯一のトクホですが、その賞味期限はどのくらいなのでしょうか?
緑でサラナの賞味期限は製造から1年間
緑でサラナの賞味期限は、製造から約1年間です。これは、砂糖・食塩・香料・保存料を一切使用していないため、長期保存ができないからです。緑でサラナは、8種類の野菜と2種類の果物を使用しており、一部の原材料にはフレッシュピューレ製法を採用しています。この製法は、生のままピューレ化し、熱をかけずにレモン汁で酵素の働きを止めることで、野菜のフレッシュ感と栄養価を損なわないようにしています。
緑でサラナの保存方法と開封後の消費期限
緑でサラナは、常温で保存できますが、直射日光や高温多湿を避けてください。また、賞味期限内であっても、開封後は冷蔵庫に入れて早めにお召し上がりください。開封後の消費期限は、製品に記載されていませんが、一般的には2~3日以内に飲みきることをおすすめします。開封後は、空気に触れることで酸化が進み、品質が劣化する可能性があります。また、微生物の繁殖も防ぐために、冷蔵庫での保存が必要です。
まとめ:緑のサラナはコレステロールを下げるのにおすすめ
以上、コレステロールを下げる特定保健用食品「緑のサラナ」についてご紹介しました。緑のサラナは、特定保健用食品として認められたSMCSを含む、野菜ジュース感覚で飲める飲料で、LDLコレステロールを下げる効果があります。また、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素も豊富で、無添加でおいしいと評判です。1日2缶を食事と一緒に飲むことで、コレステロールのバランスを整えることができます。ただし、アレルギーや妊娠、薬の服用などの場合は、注意が必要です。コレステロールが気になる方は、緑のサラナをまずは3週間試してみてください。
コレステロールを下げる野菜ランキング
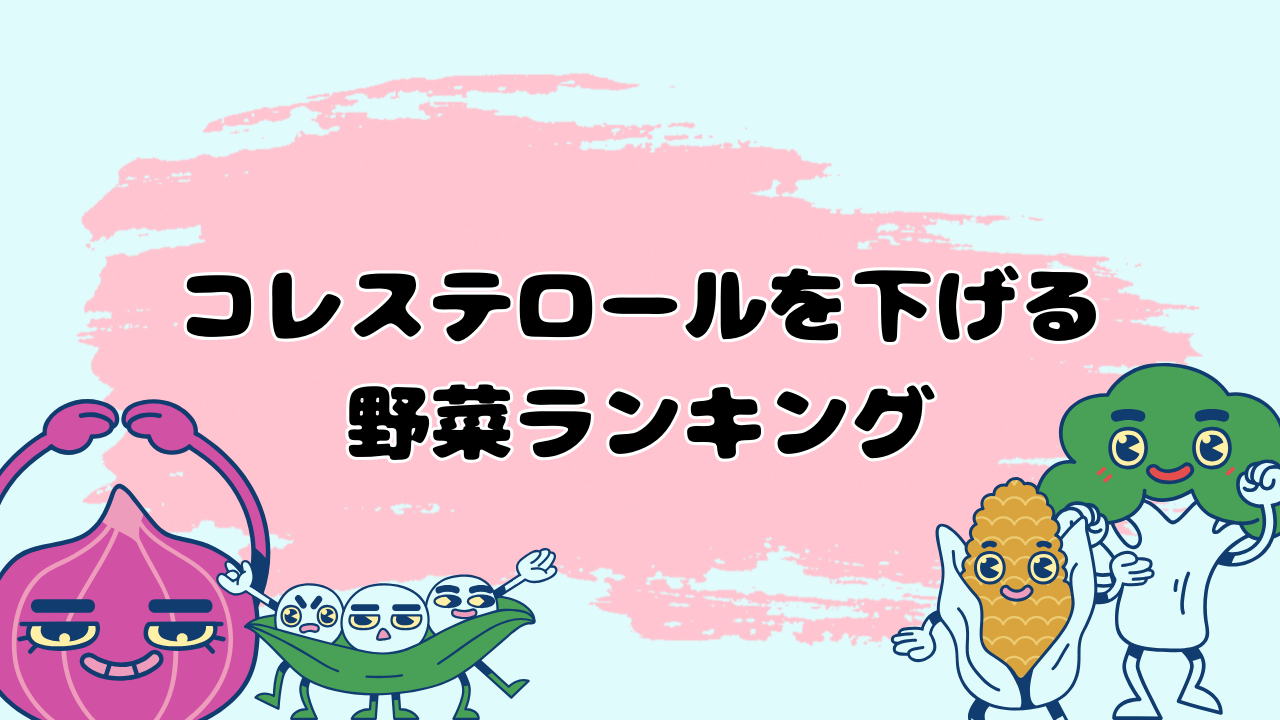
コレステロールとは、体に必要な脂質の一種ですが、血液中に過剰になると動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを高めます。コレステロール値を下げるためには、食事の見直しが重要です。特に、野菜に含まれる食物繊維やポリフェノールなどの成分は、コレステロールの吸収を抑えたり、排出を促したりする効果があります。そこで、コレステロールを下げる野菜のランキングを紹介します。このランキングは、以下の基準に基づいて作成しました。
- 野菜に含まれる食物繊維やポリフェノールなどのコレステロールを下げる成分の量
- 野菜のカロリーや脂質の量
- 野菜の食べやすさや調理のしやすさ
- 野菜の栄養価や健康効果
1位:アボカド
アボカドは、コレステロールを下げる野菜の中でもトップクラスの効果を持っています。アボカドには、食物繊維やビタミンE、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれていますが、特に注目すべきは、不飽和脂肪酸の一種であるオレイン酸です。オレイン酸は、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らし、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やす効果があります。また、オレイン酸は、血管を柔らかくする働きもあり、動脈硬化の予防にも役立ちます。アボカドは、サラダやスムージーなどに加えるだけでなく、パンに塗ったり、スープに入れたりすることもできます。ただし、アボカドはカロリーが高いので、1日に食べる量は半分程度にしましょう。
2位:オクラ
オクラは、ぬめりに含まれる水溶性食物繊維がコレステロールを下げる効果を発揮します。水溶性食物繊維は、腸内でコレステロールや胆汁酸と結合し、便と一緒に排出することで、血液中のコレステロール濃度を下げます。また、オクラには、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸も含まれています。クロロゲン酸は、コレステロールの合成を抑制する働きがあります。オクラは、生のまま食べると苦みがありますが、塩もみしたり、酢やレモン汁をかけたりすると、苦みが和らぎます。また、煮物や炒め物、スープなどにも使えます。
3位:モロヘイヤ
モロヘイヤは、オクラと同様に、ぬめりに含まれる水溶性食物繊維がコレステロールを下げる効果を持っています。モロヘイヤには、オクラの約3倍の水溶性食物繊維が含まれていると言われています。また、モロヘイヤには、ビタミンAやビタミンC、カルシウムなどの栄養素も豊富に含まれています。モロヘイヤは、和風の煮物や汁物にするのが一般的ですが、カレーやパスタなどにも合います。また、生のままサラダにしたり、ジュースにしたりすることもできます。
4位:キャベツ
キャベツは、水溶性食物繊維のほかに、不溶性食物繊維も多く含まれています。不溶性食物繊維は、腸のぜん動運動を促進し、便通を良くする効果があります。便通が良くなると、コレステロールや胆汁酸の再吸収が減り、血液中のコレステロール濃度が下がります。また、キャベツには、ポリフェノールの一種であるシナリンも含まれています。シナリンは、肝臓でのコレステロールの合成を抑制する働きがあります。キャベツは、生のままサラダにしたり、炒めたり、煮込んだり、ロールキャベツにしたりと、さまざまな料理に使えます。
5位:大豆製品
大豆製品は、大豆に含まれる大豆イソフラボンがコレステロールを下げる効果を持っています。大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た作用をする植物性エストロゲンの一種です。大豆イソフラボンは、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やすことで、動脈硬化の予防に役立ちます。また、大豆製品には、食物繊維やたんぱく質、レシチンなどの栄養素も含まれています。大豆製品は、納豆や豆腐、豆乳、味噌、醤油など、日本食に欠かせない食材です。毎日の食事に取り入れることで、コレステロール値を下げる効果が期待できます。
まとめ
コレステロールを下げる野菜のランキングを紹介しました。野菜には、食物繊維やポリフェノールなどのコレステロールを下げる成分が多く含まれています。野菜をたくさん食べることで、血液中のコレステロール濃度を適正に保ち、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを低減することができます。野菜は、生のまま食べるだけでなく、煮たり、炒めたり、スープにしたりと、さまざまな調理法で楽しむことができます。野菜の食べ方によっては、コレステロールを下げる成分の効果が変わることもあります。例えば、アボカドは加熱するとオレイン酸の含有量が減るので、生のまま食べるのがおすすめです。また、キャベツは切ってからしばらく置くとシナリンの含有量が増えるので、切ってから10分ほど経ってから食べるのが良いです。野菜の特性を知って、効果的に食べることが大切です。
以上、コレステロールを下げる野菜のランキングを紹介しました。野菜は、コレステロール値を下げるだけでなく、他の病気の予防や健康増進にも役立つ食品です。毎日の食事に野菜をたっぷりと取り入れることで、健康的な生活を送りましょう。
野菜を使用したコレステロール下げる人気レシピ

コレステロールは、血液中に存在する脂質の一種で、体に必要なホルモンや細胞膜の材料として重要な役割を果たしています。しかし、コレステロールが過剰になると、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まります。コレステロールの値は、食事や運動などの生活習慣によって大きく影響されます。特に、食事では、動物性の脂肪や油を控え、野菜や海藻などの食物繊維や大豆製品などの植物性のタンパク質を積極的に摂ることが、コレステロールを下げる効果が期待できます。ここでは、野菜を使用したコレステロール下げる人気レシピをいくつか紹介します。
コレステロールを下げる野菜スープのレシピ

野菜スープは、野菜の栄養素や食物繊維を効率的に摂ることができる料理です。野菜スープには、コレステロールを下げる効果があるとされる食材を加えると、さらに効果的です。例えば、にんにくや玉ねぎは、アリシンという成分が含まれており、コレステロールの合成を抑えたり、血液中のコレステロールを排出したりする働きがあります。また、トマトやニンジンなどの赤やオレンジ色の野菜には、β-カロテンやリコピンという抗酸化物質が豊富に含まれており、動脈硬化の予防に役立ちます。さらに、キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科の野菜には、スルフォラファンという成分が含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、肝臓でのコレステロールの代謝を促進したりする働きがあります。以下に、これらの食材を使った野菜スープのレシピを紹介します。
にんにくと玉ねぎのコンソメスープ
材料(2人分)
- にんにく 1片
- 玉ねぎ 1/2個
- オリーブオイル 大さじ1
- コンソメ顆粒 小さじ1
- 水 600ml
- 塩・こしょう 少々
- パセリ(みじん切り) 適量
作り方
1. にんにくはみじん切りにし、玉ねぎは薄切りにする。
2. 鍋にオリーブオイルを熱し、にんにくを炒める。香りが出たら玉ねぎを加えて炒める。
3. 玉ねぎがしんなりしたら、水とコンソメ顆粒を加えて沸騰させる。弱火で10分ほど煮る。
4. 塩・こしょうで味を調える。器に盛り、パセリを散らす。
トマトとニンジンのスープ
材料(4人分)
- トマト 2個
- ニンジン 1本
- 玉ねぎ 1/4個
- バター 大さじ1
- 小麦粉 大さじ2
- 牛乳 400ml
- 水 400ml
- コンソメ顆粒 小さじ2
- 塩・こしょう 少々
作り方
1. トマトは湯むきしてざく切りにし、ニンジンは皮をむいて千切りにする。玉ねぎはみじん切りにする。
2. 鍋にバターを熱し、玉ねぎを炒める。しんなりしたら小麦粉を加えて炒める。
3. 牛乳と水を少しずつ加えながら混ぜる。コンソメ顆粒を加えて沸騰させる。
4. トマトとニンジンを加えて弱火で15分ほど煮る。塩・こしょうで味を調える。
キャベツとブロッコリーのクリームスープ
材料(4人分)
- キャベツ 4枚
- ブロッコリー 1/4株
- ベーコン 2枚
- バター 大さじ1
- 小麦粉 大さじ2
- 牛乳 500ml
- 水 500ml
- コンソメ顆粒 小さじ2
- 塩・こしょう 少々
- 生クリーム 大さじ2
作り方
1. キャベツはざく切りにし、ブロッコリーは小房に分ける。ベーコンは細切りにする。
2. 鍋に水を沸騰させ、キャベツとブロッコリーをさっと茹でる。ザルに上げて水気を切る。
3. 別の鍋にバターを熱し、ベーコンを炒める。小麦粉を加えて炒める。
4. 牛乳と水を少しずつ加えながら混ぜる。コンソメ顆粒を加えて沸騰させる。
5. キャベツとブロッコリーを加えて弱火で10分ほど煮る。塩・こしょうで味を調える。
6. 生クリームを加えて混ぜる。器に盛る。
大豆や大麦を使った料理レシピ
大豆や大麦は、コレステロールを下げる効果があるとされる食材です。大豆には、イソフラボンという植物性のエストロゲンが含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、血管の弾力を保ったりする働きがあります。また、大豆には、レシチンという成分が含まれており、コレステロールの吸収を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。大麦には、β-グルカンという水溶性の食物繊維が豊富に含まれており、コレステロールや中性脂肪の値を下げる効果があります。また、大麦には、ビタミンB群やミネラルなどの栄養素も多く含まれており、血液のサラサラ効果や疲労回復効果も期待できます。以下に、大豆や大麦を使った料理のレシピを紹介します。
大豆とひじきの煮物
材料(4人分)
- 乾燥ひじき 20g
- 水 500ml
- 大豆 100g
- だし汁 300ml
- 醤油 大さじ3
- 砂糖 大さじ2
- みりん 大さじ1
- 酒 大さじ1
作り方
1. ひじきは水に10分ほど浸して戻し、水気を切る。大豆は水に一晩浸して戻す。
2. 鍋に水と大豆を入れて中火にかける。沸騰したら弱火にして20分ほど煮る。
3. だし汁、醤油、砂糖、みりん、酒を加えてひと煮立ちさせる。ひじきを加えて弱火で15分ほど煮る。
4. 汁気が少なくなるまで煮詰める。
大麦と野菜のサラダ
材料(4人分)
- 大麦 100g
- 水 400ml
- 塩 小さじ1/2
- レタス 4枚
- トマト 1個
- きゅうり 1/2本
- ドレッシング
- オリーブオイル 大さじ2
- 酢 大さじ1
- 塩・こしょう 少々
作り方
1. 大麦は水に一晩浸して戻す。
2. 鍋に水と塩を沸騰させ、大麦を加えて弱火で20分ほど煮る。ザルに上げて水気を切る。
3. レタスは手でちぎり、トマトはくし切りにし、きゅうりは薄切りにする。
4. ドレッシングの材料を混ぜ合わせる。
5. ボウルに大麦と野菜を入れてドレッシングと和える。
アブラナ科の野菜を使った料理の調理法
アブラナ科の野菜とは、キャベツやブロッコリー、カリフラワー、大根、白菜などの野菜のことです。アブラナ科の野菜には、スルフォラファンという成分が含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、肝臓でのコレステロールの代謝を促進したりする働きがあります。また、アブラナ科の野菜には、ビタミンCやカルシウムなどの栄養素も多く含まれており、免疫力の向上や骨の健康にも役立ちます。アブラナ科の野菜を使った料理の調理法は、以下のようなものがあります。
サラダ
アブラナ科の野菜は、生で食べると、スルフォラファンの効果が最大限に発揮されます。また、生で食べると、野菜のシャキシャキとした食感や甘みも楽しめます。アブラナ科の野菜をサラダにする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。ドレッシングは、オリーブオイルやレモン汁などのさっぱりとしたものがおすすめです。例えば、ブロッコリーとカリフラワーのサラダや、白菜とツナのサラダなどがあります。
スープ
アブラナ科の野菜は、スープにすると、野菜の旨みが出てコクのある味になります。また、スープにすると、野菜の食べ応えも増します。アブラナ科の野菜をスープにする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。鍋に水やだし汁を入れて沸騰させ、野菜を加えて煮ます。塩・こしょうやコンソメなどで味を調えます。クリームやチーズを加えると、より濃厚な味になります。例えば、キャベツとブロッコリーのクリームスープや、大根とチーズのスープなどがあります。
炒め物
アブラナ科の野菜は、炒め物にすると、野菜の香りや色が引き立ちます。また、炒め物にすると、野菜の栄養素が失われにくくなります。アブラナ科の野菜を炒め物にする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。フライパンに油を熱し、野菜を炒めます。醤油やオイスターソースなどで味をつけます。肉や卵などを加えると、タンパク質も摂れます。例えば、キャベツとベーコンの炒め物や、ブロッコリーと卵の炒め物などがあります。
海藻を使った料理の作り方
海藻は、コレステロールを下げる効果があるとされる食材です。海藻には、アルギン酸という水溶性の食物繊維が豊富に含まれており、コレステロールや中性脂肪の吸収を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。また、海藻には、ヨウ素やカリウムなどのミネラルやビタミンも多く含まれており、甲状腺の機能の正常化や血圧の調整などにも役立ちます。海藻を使った料理の作り方は、以下のようなものがあります。
和え物
海藻は、和え物にすると、海藻のプチプチとした食感や風味が楽しめます。また、和え物にすると、海藻の栄養素がそのまま摂れます。海藻を和え物にする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。酢や醤油などの調味料と和えます。ごまやわさびなどを加えると、より風味が増します。例えば、わかめときゅうりの酢の物や、もずくと豆腐の和え物などがあります。
煮物
海藻は、煮物にすると、海藻の旨みが出てコクのある味になります。また、煮物にすると、海藻の食べ応えも増します。海藻を煮物にする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。鍋に水やだし汁を入れて沸騰させ、海藻を加えて煮ます。醤油やみりんなどで味をつけます。肉や野菜などを加えると、栄養バランスも良くなります。例えば、昆布と鶏肉の煮物や、ひじきと人参の煮物などがあります。
揚げ物
海藻は、揚げ物にすると、海藻の香ばしさやサクサクとした食感が楽しめます。また、揚げ物にすると、海藻の水分が飛んでカロリーが低くなります。海藻を揚げ物にする場合は、水洗いして水気を切り、食べやすい大きさに切ります。小麦粉や片栗粉などの衣をつけて揚げます。塩や酢などで味をつけます。例えば、昆布の天ぷらや、ひじきのかき揚げなどがあります。
【ためしてガッテンで紹介】コレステロールを下げるレシピ
ためしてガッテンは、NHKの科学教養番組で、健康や生活に役立つ情報を分かりやすく紹介しています。この番組では、コレステロールを下げるレシピも何度か紹介しています。ここでは、その中からいくつかのレシピを紹介します。
バナナと豆乳のスムージー
材料(1人分)
- バナナ 1本
- 豆乳 200ml
- ハチミツ 小さじ1
作り方
1. バナナは皮をむいて切る。
2. ミキサーにバナナと豆乳とハチミツを入れて撹拌する。
3. グラスに注ぐ。
コレステロールを下げる効果
バナナには、ペクチンという水溶性の食物繊維が含まれており、コレステロールの吸収を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。また、バナナには、カリウムというミネラルも多く含まれており、血圧の上昇を防いだり、血液の循環を良くしたりする働きがあります。豆乳には、大豆と同様にイソフラボンやレシチンという成分が含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、吸収を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。ハチミツには、フラクトースという糖分が含まれており、コレステロールの代謝を促進したり、血液の粘度を下げたりする働きがあります。
きのこと玉ねぎのマリネ
材料(4人分)
- しめじ 1パック
- えのき 1パック
- 玉ねぎ 1/2個
- マリネ液
- 酢 大さじ4
- 醤油 大さじ2
- 砂糖 大さじ2
- 水 100ml
- にんにく 1片
- 生姜 1片
作り方
1. しめじとえのきは根元を切り落としてほぐす。玉ねぎは薄切りにする。にんにくと生姜はみじん切りにする。
2. 鍋にマリネ液の材料を入れて沸騰させる。玉ねぎを加えて5分ほど煮る。
3. きのこを加えてさらに5分ほど煮る。
4. ボウルに移して冷まし、冷蔵庫で冷やす。
コレステロールを下げる効果
きのこには、キチンという不溶性の食物繊維が含まれており、コレステロールの吸収を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。また、きのこには、エリタデニンという成分が含まれており、コレステロールの合成を抑えたり、血液中のコレステロールを減らしたりする働きがあります。玉ねぎには、アリシンという成分が含まれており、コレステロールの合成を抑えたり、排出を促したりする働きがあります。酢には、酢酸という成分が含まれており、コレステロールの吸収を抑えたり、中性脂肪の分解を促したりする働きがあります。にんにくと生姜には、アリシンやジンゲロールなどの辛味成分が含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、血液の流れを良くしたりする働きがあります。醤油には、イソフラボンやサポニンなどの成分が含まれており、コレステロールの酸化を防いだり、排出を促したりする働きがあります。
食事習慣によるコレステロール管理
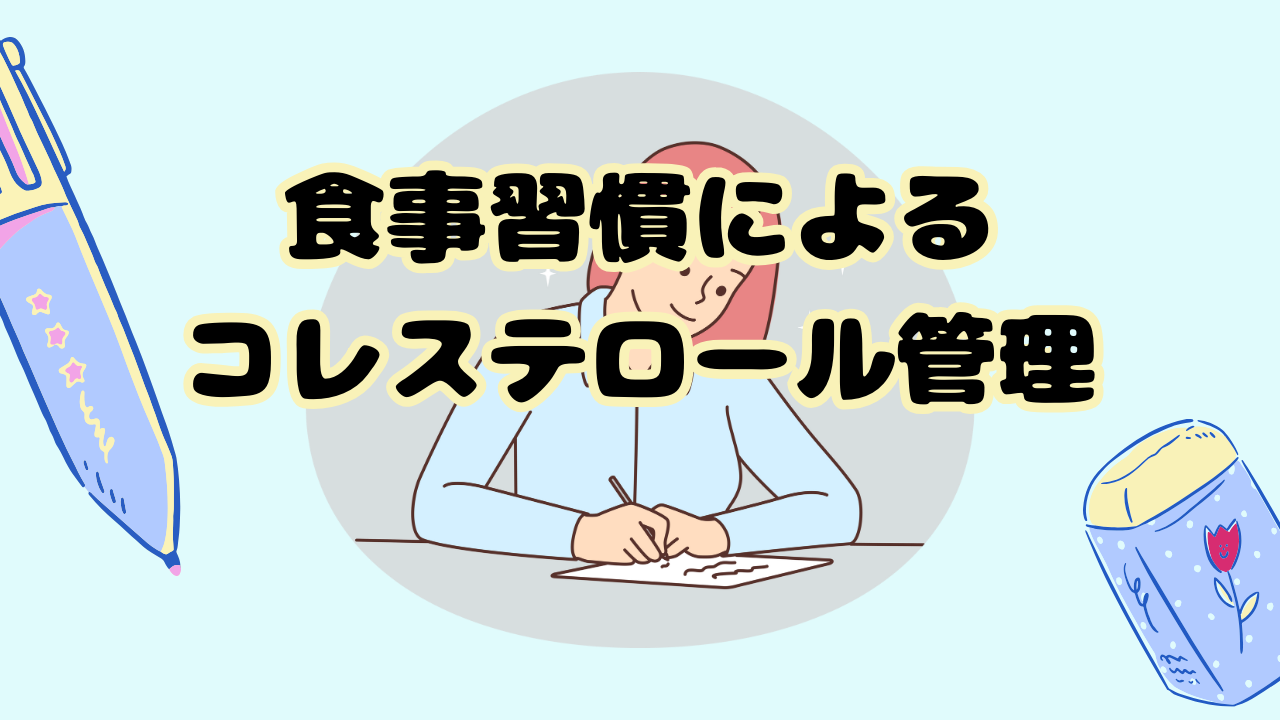
こんにちは。ここでは食事習慣によるコレステロールの管理方法について、管理栄養士の私がわかりやすく解説していますが、個人の体質や病歴などによって異なる場合がありますので、必ず医師や専門家に相談してください。
コレステロールが高い人が食べてはいけないもの
動物性脂肪はコレステロールの元凶!摂取量を減らそう
コレステロールは体内で合成されるほか、食事からも摂取されます。コレステロールが高い人は、食事からの摂取量を減らすことが重要です。特に、動物性脂肪にはコレステロールが多く含まれていますので、注意が必要です。動物性脂肪が多く含まれる食品は以下のとおりです。
- 肉類(牛肉、豚肉、鶏肉、レバーなど)
- 卵
- 乳製品(バター、チーズ、生クリーム、アイスクリームなど)
- 内臓類(レバー、ハツ、ミノなど)
- 魚介類(エビ、カニ、イカ、タコなど)
これらの食品は、コレステロールだけでなく、飽和脂肪酸も多く含まれています。飽和脂肪酸は、コレステロールの合成を促進する働きがありますので、摂りすぎると血中コレステロール値を上げる可能性があります。動物性脂肪の摂取量は、一日に総カロリーの10%以下に抑えることが推奨されています。
揚げ物やスナック菓子も要注意!トランス脂肪酸はコレステロールの敵
コレステロールが高い人が食べてはいけないものとして、もう一つ忘れてはならないのがトランス脂肪酸です。トランス脂肪酸は、植物油を加工する際に生成される不自然な形の脂肪酸で、コレステロールの悪玉LDLコレステロールを増やし、善玉HDLコレステロールを減らすという、二重の悪影響を及ぼします。トランス脂肪酸は、以下のような食品に多く含まれています。
- 揚げ物(天ぷら、フライドチキン、ドーナツなど)
- スナック菓子(ポテトチップス、クッキー、ケーキなど)
- マーガリンやショートニング
- ファストフードやインスタント食品
トランス脂肪酸の摂取量は、一日に総カロリーの1%以下に抑えることが推奨されています。トランス脂肪酸の含有量は、食品の成分表や栄養成分表示をチェックすることで確認できます。また、食品の原材料に「植物油(一部にトランス脂肪酸を含む)」や「加工油脂」などと記載されている場合は、トランス脂肪酸が含まれている可能性が高いですので、避けるようにしましょう。
コレステロールが高い人が食べてはいけないもののまとめ
コレステロールが高い人が食べてはいけないものは、動物性脂肪とトランス脂肪酸が多く含まれる食品です。これらの食品は、血中コレステロール値を上げるとともに、動脈硬化や心臓病などのリスクを高める可能性があります。食事からのコレステロール摂取量は、一日に300mg以下に抑えることが目安です。動物性脂肪の摂取量は、一日に総カロリーの10%以下に、トランス脂肪酸の摂取量は、一日に総カロリーの1%以下に抑えることが大切です。食品の成分表や栄養成分表示を見て、コレステロールや脂肪の含有量を確認する習慣をつけましょう。
朝食でのコレステロールを下げる食材の取り入れ方

朝食はコレステロール管理のチャンス!食物繊維やオメガ3脂肪酸を摂ろう
コレステロールが高い人にとって、朝食はコレステロール管理に有効な食事です。朝食には、コレステロールを下げる効果がある食物繊維やオメガ3脂肪酸を積極的に摂ることがおすすめです。食物繊維は、コレステロールを吸着して便と一緒に排出する働きがあります。オメガ3脂肪酸は、悪玉LDLコレステロールを減らし、善玉HDLコレステロールを増やすという、コレステロールのバランスを改善する効果があります。食物繊維やオメガ3脂肪酸が多く含まれる食材は以下のとおりです。
食物繊維
- 穀物類(玄米、オートミール、全粒粉パンなど)
- 野菜類(ほうれん草、キャベツ、にんじんなど)
- 果物類(りんご、バナナ、オレンジなど)
- 豆類(大豆、ひよこ豆、レンズ豆など)
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじきなど)
- ナッツ類(くるみ、アーモンド、ピスタチオなど)
オメガ3脂肪酸
- 青魚類(サバ、サーモン、イワシなど)
- 亜麻仁油やえごま油などの植物油
- チアシードや亜麻仁などのスーパーフード
これらの食材を朝食に取り入れることで、コレステロールを下げる効果が期待できます。例えば、以下のようなメニューがおすすめです。
- オートミールに刻んだりんごやナッツをトッピングし、亜麻仁油をかける
- 全粒粉パンにアボカドやチーズをのせ、サバの水煮缶を添える
- 玄米とほうれん草の炒め物にサーモンを加え、チアシードをふりかける
朝食でのコレステロールを下げる食材の取り入れ方のまとめ
朝食はコレステロール管理に有効な食事です。朝食には、食物繊維やオメガ3脂肪酸を多く含む食材を摂ることがおすすめです。食物繊維は、コレステロールを便と一緒に排出する効果があります。オメガ3脂肪酸は、コレステロールのバランスを改善する効果があります。穀物類、野菜類、果物類、豆類、海藻類、ナッツ類などの食物繊維豊富な食材や、青魚類、植物油、スーパーフードなどのオメガ3脂肪酸豊富な食材を朝食に取り入れることで、コレステロールを下げる効果が期待できます。朝食は、一日の始まりにコレステロール管理をするチャンスです。ぜひ、コレステロールを下げる食材を取り入れたバランスの良い朝食を楽しみましょう。
コレステロールを下げる飲み物を用いた管理方法
コレステロールを下げる飲み物は存在する?効果的な飲み方と注意点
コレステロールを下げる飲み物として、よく聞くのが紅茶や緑茶、豆乳などです。これらの飲み物には、コレステロールを下げる効果があると言われていますが、本当にそうなのでしょうか?そして、どのように飲むのが効果的なのでしょうか?ここでは、コレステロールを下げる飲み物について、その効果と飲み方、注意点などを解説します。
紅茶
- 紅茶には、ポリフェノールという抗酸化物質が含まれています。ポリフェノールには、コレステロールの酸化を防ぎ、悪玉LDLコレステロールを減らす効果があると言われています 。
- 紅茶を飲むときは、砂糖やミルクを加えないのがベストです。砂糖やミルクは、カロリーや脂肪の摂取量を増やし、コレステロールの上昇につながる可能性があります。紅茶は、なるべくストレートで飲むか、はちみつやレモンを少量加える程度にしましょう。
- 紅茶の摂取量は、一日に3~5杯程度が目安です。紅茶にはカフェインも含まれていますので、飲みすぎると不眠や動悸などの副作用が出る可能性があります。また、紅茶は鉄の吸収を妨げる作用がありますので、食事と一緒に飲むのではなく、食間に飲むようにしましょう。
緑茶
- 緑茶にも、紅茶と同様にポリフェノールが含まれています。緑茶のポリフェノールの中でも、カテキンという種類のものが特にコレステロールを下げる効果が高いと言われています 。カテキンは、コレステロールの吸収を抑え、排出を促す働きがあります。
- 緑茶を飲むときは、紅茶と同じく、砂糖やミルクを加えないのがベストです。また、緑茶は、水温や抽出時間によってカテキンの含有量が変わります。カテキンを多く摂取するには、水温は80℃以下、抽出時間は1分以内にするのがおすすめです。
- 緑茶の摂取量は、一日に3~5杯程度が目安です。緑茶にもカフェインが含まれていますので、飲みすぎに注意しましょう。また、緑茶も鉄の吸収を妨げる作用がありますので、食事と一緒に飲むのではなく、食間に飲むようにしましょう。
豆乳
- 豆乳には、大豆イソフラボンという植物性エストロゲンが含まれています。大豆イソフラボンには、コレステロールの合成を抑え、悪玉LDLコレステロールを減らし、善玉HDLコレステロールを増やす効果があると言われています 。
- 豆乳を飲むときは、無調整のものを選ぶのがベストです。無調整の豆乳は、大豆の成分がそのまま残っていますので、大豆イソフラボンの効果が高いです。調整豆乳や加糖豆乳は、水や砂糖などが加えられていますので、大豆イソフラボンの含有量が低くなっています。また、味付きの豆乳は、カロリーや脂肪の摂取量を増やす可能性がありますので、注意が必要です。
- 豆乳の摂取量は、一日に200~300ml程度が目安です。豆乳には、タンパク質やカルシウムなどの栄養素も含まれていますので、牛乳の代わりに飲むことができます。また、豆乳は、コーヒーや紅茶、シリアルなどに混ぜて飲むこともできます。
コレステロールを下げる飲み物を用いた管理方法のまとめ
コレステロールを下げる飲み物として、紅茶や緑茶、豆乳が有効です。これらの飲み物には、コレステロールの酸化を防いだり、吸収や合成を抑えたり、排出を促したりする効果があると言われています。紅茶や緑茶は、砂糖やミルクを加えずにストレートで飲むのがベストです。豆乳は、無調整のものを選ぶのがベストです。これらの飲み物の摂取量は、一日に3~5杯程度が目安です。飲みすぎに注意しましょう。また、紅茶や緑茶は、鉄の吸収を妨げる作用がありますので、食事と一緒に飲むのではなく、食間に飲むようにしましょう。コレステロールを下げる飲み物を用いた管理方法は、食事や運動と併用することで、より効果的になります。ぜひ、コレステロールを下げる飲み物を食生活に取り入れて、健康的なコレステロール値を目指しましょう。
コレステロール下げる飲み物ランキング
コレステロールを下げる飲み物の効果を比較してランキングにしてみました
コレステロールを下げる飲み物として、紅茶や緑茶、豆乳などが有効だということは、前の記事で解説しました。では、これらの飲み物の中で、どれが一番コレステロールを下げる効果が高いのでしょうか?ここでは、コレステロールを下げる飲み物の効果を比較して、ランキングにしてみました。ランキングの基準は、以下のとおりです。
- コレステロールを下げる効果の強さ
- コレステロールを下げる成分の含有量
- コレステロールを下げる成分の種類と作用
- コレステロールを下げる飲み物の摂取方法や注意点
それでは、コレステロール下げる飲み物ランキングを発表します。
第3位:紅茶
コレステロール下げる飲み物ランキングの第3位は、紅茶です。紅茶には、ポリフェノールという抗酸化物質が含まれています。ポリフェノールには、コレステロールの酸化を防ぎ、悪玉LDLコレステロールを減らす効果があると言われています。紅茶のポリフェノールの含有量は、一杯あたり約100mgです。紅茶のポリフェノールの種類は、テアフラビンやテアルビジンなどです。これらのポリフェノールは、コレステロールの酸化を防ぐことで、動脈硬化や心臓病などのリスクを低減すると考えられています。紅茶を飲むときは、砂糖やミルクを加えないのがベストです。紅茶の摂取量は、一日に3~5杯程度が目安です。
第2位:緑茶
コレステロール下げる飲み物ランキングの第2位は、緑茶です。緑茶にも、紅茶と同様にポリフェノールが含まれています。緑茶のポリフェノールの含有量は、一杯あたり約200mgです。緑茶のポリフェノールの種類は、カテキンというものが主です。カテキンは、コレステロールの吸収を抑え、排出を促す働きがあります。カテキンの中でも、エピガロカテキンガレート(EGCG)というものが特に強い効果を持つと言われています。緑茶を飲むときは、水温は80℃以下、抽出時間は1分以内にするのがおすすめです。緑茶の摂取量は、一日に3~5杯程度が目安です。
第1位:豆乳
コレステロール下げる飲み物ランキングの第1位は、豆乳です。豆乳には、大豆イソフラボンという植物性エストロゲンが含まれています。大豆イソフラボンには、コレステロールの合成を抑え、悪玉LDLコレステロールを減らし、善玉HDLコレステロールを増やす効果があると言われています。豆乳の大豆イソフラボンの含有量は、一杯あたり約30mgです。大豆イソフラボンの種類は、ダイズエクインやゲニステインなどです。これらの大豆イソフラボンは、コレステロールのバランスを改善することで、動脈硬化や心臓病などのリスクを低減すると考えられています。豆乳を飲むときは、無調整のものを選ぶのがベストです。豆乳の摂取量は、一日に200~300ml程度が目安です。
コレステロール下げる飲み物ランキングのまとめ
コレステロール下げる飲み物ランキングを発表しました。第3位は紅茶、第2位は緑茶、第1位は豆乳でした。これらの飲み物には、コレステロールを下げる効果があると言われている成分が含まれています。それぞれの飲み物の効果や飲み方、注意点などを理解して、適切に摂取することが大切です。コレステロールを下げる飲み物は、食事や運動と併用することで、より効果的になります。ぜひ、コレステロールを下げる飲み物を食生活に取り入れて、健康的なコレステロール値を目指しましょう。
青魚やDHA, EPA含有食品はコレステロールのバランスを整える!摂取のメリットとおすすめの食品
コレステロールを下げる食品として、青魚やDHA, EPA含有食品が有効だということは、多くの人が知っていると思います。しかし、なぜ青魚やDHA, EPA含有食品がコレステロールに良いのでしょうか?そして、どのような食品をどのくらい摂取すればいいのでしょうか?ここでは、青魚やDHA, EPA含有食品の摂取とコレステロールの関係について、そのメリットとおすすめの食品を紹介します。
青魚やDHA, EPA含有食品のメリット
青魚やDHA, EPA含有食品には、オメガ3脂肪酸という不飽和脂肪酸が多く含まれています。オメガ3脂肪酸には、コレステロールの悪玉LDLコレステロールを減らし、善玉HDLコレステロールを増やすという、コレステロールのバランスを整える効果があります 。また、オメガ3脂肪酸には、血液の流れを改善し、血栓や動脈硬化を予防する効果もあります 。オメガ3脂肪酸の中でも、DHAとEPAという種類のものが特に強い効果を持つと言われています。DHAとEPAは、コレステロールだけでなく、中性脂肪や血圧などの血液中の脂質や塩分の量にも影響を与えます。DHAとEPAは、中性脂肪や血圧を下げる効果がありますので、高血圧や高脂血症などの生活習慣病の予防や改善にも役立ちます 。
青魚やDHA, EPA含有食品のおすすめ
青魚やDHA, EPA含有食品の摂取量は、一日にDHAとEPAの合計で1g程度が目安です。DHAとEPAの含有量は、食品によって異なりますが、一般的には、以下のような食品がおすすめです。
- 青魚類(サバ、サーモン、イワシ、アジなど)
- 魚油や魚肝油などのサプリメント
- DHAやEPAが添加された食品(牛乳、ヨーグルト、マーガリンなど)
青魚やDHA, EPA含有食品を摂取するときは、調理方法や保存方法に注意しましょう。オメガ3脂肪酸は、熱や光に弱い性質がありますので、揚げ物や焼き物などの高温調理は避けるようにしましょう。また、魚油や魚肝油などのサプリメントは、冷暗所に保存し、賞味期限を守るようにしましょう。
青魚やDHA, EPA含有食品の摂取とコレステロールのまとめ
青魚やDHA, EPA含有食品には、オメガ3脂肪酸という不飽和脂肪酸が多く含まれています。オメガ3脂肪酸には、コレステロールのバランスを整える効果があります。また、血液の流れを改善し、血栓や動脈硬化を予防する効果もあります。オメガ3脂肪酸の中でも、DHAとEPAという種類のものが特に強い効果を持つと言われています。DHAとEPAは、中性脂肪や血圧などの血液中の脂質や塩分の量にも影響を与えます。青魚やDHA, EPA含有食品の摂取量は、一日にDHAとEPAの合計で1g程度が目安です。青魚類、魚油や魚肝油などのサプリメント、DHAやEPAが添加された食品などがおすすめです。青魚やDHA, EPA含有食品を摂取するときは、調理方法や保存方法に注意しましょう。青魚やDHA, EPA含有食品を摂取することで、コレステロールを下げるだけでなく、心血管系の健康にも貢献できます。ぜひ、青魚やDHA, EPA含有食品を食生活に取り入れて、健康的なコレステロール値を目指しましょう。
コレステロールを下げるための全体的な対策

コレステロールは、細胞膜やホルモンなどの材料として必要な物質ですが、血液中に過剰になると動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを高めます。コレステロール値を下げるためには、食事や運動などの生活習慣の改善が重要です。ここでは、自宅でできるコレステロールを下げる運動や筋トレ、食物繊維や不飽和脂肪酸などの有効成分の働き、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を避けるための注意点について、管理栄養士が栄養面からわかりやすく解説します。
自宅で出来る!コレステロールを下げる運動・筋トレ

運動は、コレステロール値を下げる効果があります。運動によって、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らし、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やすことができます。また、運動は体重や体脂肪を減らすことにもつながり、肥満や糖尿病などの動脈硬化の危険因子を改善することができます。
コレステロールを下げるためには、有酸素運動と筋力トレーニングの両方がおすすめです。有酸素運動は、心肺機能を高め、エネルギー消費を促進する運動です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などが代表的な有酸素運動です。筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を上げる運動です。ダンベルやゴムバンドなどを使ったトレーニングや、自重を使ったスクワットや腕立て伏せなどが筋力トレーニングになります。
自宅でできるコレステロールを下げる運動・筋トレのポイントは以下のとおりです。
頻度
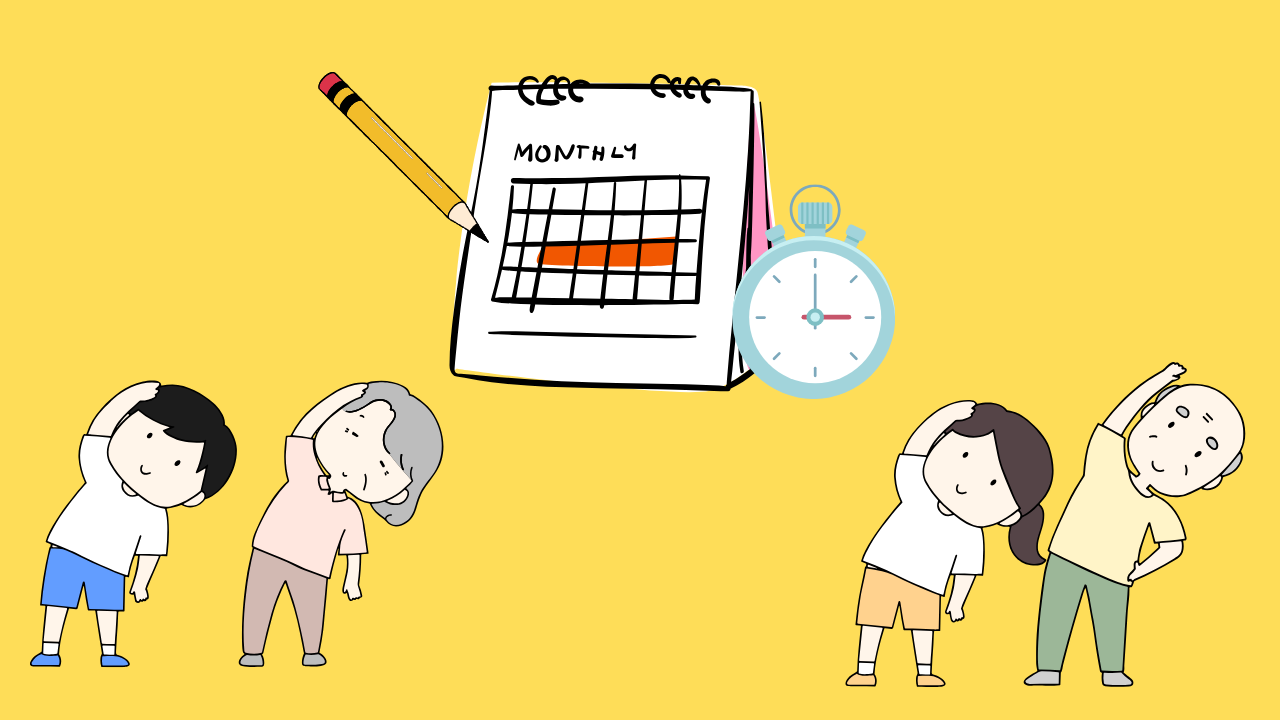
頻度は週に3~5回、1回あたり30~60分を目標にしましょう。週に150分以上の運動がコレステロールの改善に効果的とされています。
強度

強度は自分の体力に合わせて調整しましょう。息が切れるほどの運動は必要ありませんが、少し汗をかくくらいの運動が望ましいです。運動中の心拍数は、最大心拍数の50~70%が目安です。
有酸素運動と筋力トレーニング
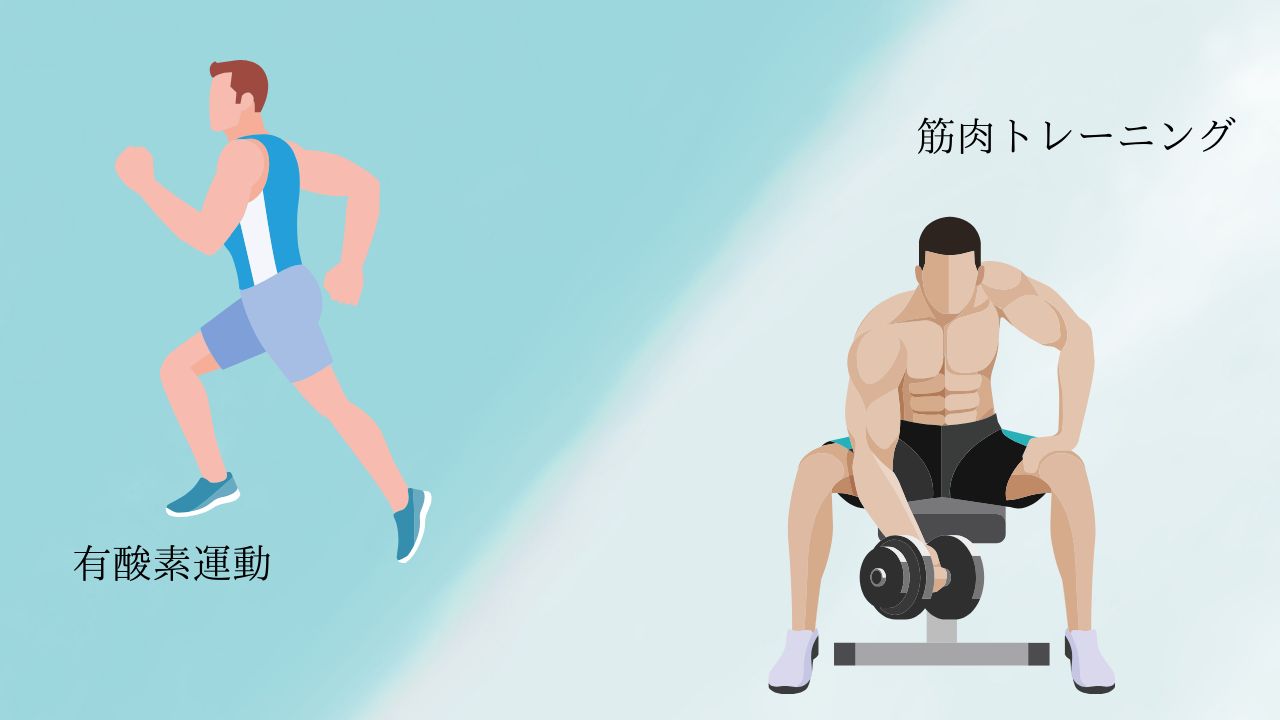
有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせましょう。有酸素運動の前後に筋力トレーニングを行うと、より効果的にコレステロールを下げることができます。
水分補給

運動の前後に水分補給をしましょう。運動によって失われた水分を補うことで、血液の流れを良くし、コレステロールの排出を促進することができます。水やお茶などの無糖の飲み物がおすすめです。
運動の効果を高める食事

運動の効果を高めるために、食事にも気をつけましょう。運動の前には、炭水化物やタンパク質を含む食事をとることで、エネルギー源となる糖や筋肉の材料となるアミノ酸を補給することができます。運動の後には、筋肉の回復に必要なタンパク質を含む食事をとることで、筋肉量を増やすことができます。
食物繊維や不飽和脂肪酸などの有効成分の働き
食事は、コレステロール値を下げるためにも重要な要素です。食事から摂取するコレステロールや脂質は、血中のコレステロール濃度に影響を与えます。特に、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、悪玉コレステロールを増やす作用があるため、摂取量を減らす必要があります。一方で、食物繊維や不飽和脂肪酸は、コレステロールを下げる効果があるため、積極的に摂取することが望ましいです。
食物繊維は、水溶性と不溶性に分けられます。水溶性食物繊維は、水に溶けて粘り気のあるゲル状になります。このゲル状の食物繊維は、胆汁酸と結合して体外に排出することで、コレステロールの吸収を抑えるとともに、肝臓でのコレステロールの合成を減らすことができます。水溶性食物繊維は、大豆やオートミール、こんにゃく、果物などに多く含まれます。
不溶性食物繊維は、水に溶けないため、腸内で発酵されます。この発酵によって、短鎖脂肪酸という物質が生成されます。短鎖脂肪酸は、腸の働きを活性化させるとともに、肝臓でのコレステロールの合成を抑制することができます。不溶性食物繊維は、玄米や全粒粉、野菜、海藻などに多く含まれます。
不飽和脂肪酸は、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられます。一価不飽和脂肪酸は、オリーブ油やアボカド、ナッツなどに多く含まれます。一価不飽和脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やすことができます。
多価不飽和脂肪酸は、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸に分けられます。オメガ3脂肪酸は、青魚や亜麻仁油、チアシードなどに多く含まれます。オメガ3脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やすだけでなく、血液の流れを改善し、血栓の形成を防ぐことができます。オメガ6脂肪酸は、植物油やナッツ、種子などに多く含まれます。オメガ6脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らす効果がありますが、過剰に摂取すると炎症を引き起こす可能性があるため、摂取量に注意する必要があります。
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を避けるための注意点

飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、コレステロール値を上げる原因となる脂質です。飽和脂肪酸は、動物性の脂肪や乳製品、ココナッツオイルなどに多く含まれます。トランス脂肪酸は、人工的に加工された油やマーガリン、ショートニング、揚げ物や菓子などに多く含まれます。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロールを減らすことで、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高めます。
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を避けるためには、以下のような工夫をしましょう。
- 肉や乳製品は、低脂肪のものを選びましょう。皮や脂身は取り除きましょう。チーズやバターは控えめにしましょう。
- 油は、オリーブ油や菜種油などの不飽和脂肪酸が多いものを選びましょう。油の量は少なめにしましょう。揚げ物や炒め物は控えめにしましょう。
- マーガリンやショートニングは、トランス脂肪酸が多いので避けましょう。バターも飽和脂肪酸が多いので注意しましょう。
- 菓子やスナックは、トランス脂肪酸や飽和脂肪酸が多いので、できるだけ控えましょう。甘いものが食べたいときは、果物やヨーグルトなどを選びましょう。
まとめ
コレステロールを下げるためには、食事や運動などの生活習慣の改善が必要です。運動は、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を行うことで、コレステロールのバランスを整えることができます。食事は、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を減らし、食物繊維や不飽和脂肪酸を増やすことで、コレステロールの吸収や合成を抑えることができます。これらの対策を継続的に行うことで、コレステロール値を下げることができます。コレステロール値は、定期的に検査して確認しましょう。
悪玉コレステロールを下げる食品一覧

悪玉コレステロールとは、血液中に過剰に存在すると、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを高めるコレステロールの一種です。悪玉コレステロールの値を下げるためには、食事の内容や量に気を付けることが大切です。ここでは、悪玉コレステロールを下げる効果が期待できる食品や飲み物をご紹介します。
ヨーグルトや飲み物で悪玉コレステロールを下げる
ヨーグルトや飲み物には、悪玉コレステロールを下げる成分が含まれているものがあります。例えば、以下のようなものがあります。
ヨーグルト:
ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内でコレステロールを分解する働きがあります。特に、ガセリ菌SP株やビフィズス菌BB536などの特定の乳酸菌は、悪玉コレステロールを低下させる効果が高いとされています。ヨーグルトを毎日食べることで、悪玉コレステロールの値を改善することができる可能性があります。
豆乳:
豆乳には、大豆たんぱく質やサポニン、レシチンなどの成分が含まれています。これらの成分は、コレステロールの吸収を抑えたり、悪玉コレステロールを排出したりする効果があります。豆乳は牛乳の代わりに飲んだり、料理に使ったりすることで、コレステロールの摂取量を減らすことができます。
緑茶:
緑茶には、カテキンというポリフェノールが豊富に含まれています。カテキンは、コレステロールの合成を抑制したり、コレステロールの吸収を阻害したりする効果があります。緑茶を毎日飲むことで、悪玉コレステロールの値を下げることができる可能性があります。
これらのヨーグルトや飲み物は、手軽に摂取できる上に、他の栄養素も含まれているので、健康にも良いと言えます。ただし、砂糖やミルクなどが添加されているものは、カロリーや糖質が多くなるので、飲み過ぎには注意しましょう。
豊富に含まれる食品とその摂取方法
悪玉コレステロールを下げる効果が期待できる食品には、以下のようなものがあります。
大豆製品:
大豆製品には、大豆たんぱく質やサポニン、レシチンなどの成分が含まれています。これらの成分は、コレステロールの吸収を抑えたり、悪玉コレステロールを排出したりする効果があります。大豆製品は、豆腐や納豆、味噌、豆乳など様々な形で摂取できます。大豆製品を毎日食べることで、悪玉コレステロールの値を下げることができる可能性があります。
魚介類:
魚介類には、オメガ3脂肪酸という不飽和脂肪酸が含まれています。オメガ3脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らすだけでなく、善玉コレステロールを増やす効果もあります。魚介類は、青魚やイワシ、サバ、サーモン、マグロなどがオメガ3脂肪酸を多く含んでいます。魚介類を週に2~3回食べることで、悪玉コレステロールの値を改善することができる可能性があります。
野菜や果物:
野菜や果物には、水溶性食物繊維やポリフェノールなどの成分が含まれています。これらの成分は、コレステロールの吸収を阻害したり、悪玉コレステロールの酸化を防いだりする効果があります。野菜や果物は、色や種類によって含まれる成分が異なるので、バランスよく摂取することが大切です。野菜や果物を1日に350g以上食べることで、悪玉コレステロールの値を下げることができる可能性があります。
これらの食品は、悪玉コレステロールを下げるだけでなく、他の栄養素も豊富に含まれているので、健康にも良いと言えます。ただし、調理法や食べ合わせによっては、効果が減少する場合もあります。例えば、大豆製品や魚介類を油で揚げたり、野菜や果物にマヨネーズやドレッシングをかけたりすると、飽和脂肪酸や糖質が増えてしまいます。また、コレステロールや飽和脂肪酸の多い食品と一緒に食べると、効果が相殺されてしまう可能性もあります。調理法や食べ合わせにも気を付けて、悪玉コレステロールを下げる食品を効果的に摂取しましょう。
悪玉コレステロール逆効果の食品の注意
悪玉コレステロールを下げる食品を摂取することは大切ですが、逆に悪玉コレステロールを上げる食品を摂りすぎると、効果がなくなってしまいます。悪玉コレステロールを上げる食品には、以下のようなものがあります。
コレステロールの多い食品:
コレステロールの多い食品としては、卵黄や魚卵、ウナギ、レバーなどが挙げられます。これらの食品は、コレステロールの摂取量を増やすだけでなく、悪玉コレステロールの合成を促進する効果もあります。コレステロールの多い食品は、1日に300mg以下に抑えることが推奨されています。卵黄は1個に約200mg、魚卵は大さじ1杯に約100mg、ウナギは100gに約150mg、レバーは100gに約400mgのコレステロールが含まれています。これらの食品を食べるときは、量や頻度に注意しましょう。
飽和脂肪酸の多い食品:
飽和脂肪酸の多い食品としては、バターやチーズ、生クリーム、ラード、ベーコン、ステーキなどが挙げられます。飽和脂肪酸は、悪玉コレステロールの合成を促進する効果があります。飽和脂肪酸の多い食品は、1日にエネルギーの7%以下に抑えることが推奨されています。バターは大さじ1杯に約8g、チーズは20gに約3g、生クリームは大さじ1杯に約2g、ラードは大さじ1杯に約13g、ベーコンは1枚に約1g、ステーキは100gに約5gの飽和脂肪酸が含まれています。これらの食品を食べるときは、量や頻度に注意しましょう。
糖質の多い食品:
糖質の多い食品としては、白米やパン、パスタ、菓子パン、ケーキ、アイスクリームなどが挙げられます。糖質は、インスリンの分泌を促進することで、悪玉コレステロールの合成を促進する効果があります。糖質の多い食品は、1日にエネルギーの50~60%以下に抑えることが推奨されています。白米は茶碗1杯に約40g、パンは1枚に約20g、パスタは茶碗1杯に約30g、菓子パンは1個に約30g、ケーキは1切れに約20g、アイスクリームはカップ1個に約15gの糖質が含まれています。これらの食品を食べるときは、量や頻度に注意しましょう。
これらの食品は、悪玉コレステロールを上げるだけでなく、他の健康問題も引き起こす可能性があります。例えば、コレステロールや飽和脂肪酸の多い食品は、肥満や糖尿病などのリスクを高めます。糖質の多い食品は、虫歯や肌荒れなどのリスクを高めます。これらの食品は、できるだけ控えるか、低脂肪や低糖質のものに置き換えることが望ましいです。
悪玉コレステロールを下げる食品一覧のまとめ
悪玉コレステロールを下げるためには、食事の内容や量に気を付けることが大切です。悪玉コレステロールを下げる効果が期待できる食品や飲み物は、以下のようなものがあります。
ヨーグルトや飲み物:
乳酸菌や大豆たんぱく質やカテキンなどの成分が含まれているものが良いです。
大豆製品や魚介類や野菜や果物:
大豆たんぱく質やサポニンやレシチンやオメガ3脂肪酸や水溶性食物繊維やポリフェノールなどの成分が含まれているものが良いです。
コレステロールや飽和脂肪酸や糖質の多い食品:
卵黄や魚卵やウナギやレバーやバターやチーズや生クリームやラードやベーコンやステーキや白米やパンやパスタや菓子パンやケーキやアイスクリームなどは控えるか、低脂肪や低糖質のものに置き換えることが望ましいです。
以上が悪玉コレステロールを下げる食品一覧についての記事です。悪玉コレステロールの値を改善することで、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを低減することができます。食事に気を付けて、健康的な生活を送りましょう。